岩野建設専門技能訓練学園とは
i[愛]をもって、
i[自分]の力を発揮する
自立した人材を育てます。
「岩野建設専門技能訓練学園」は、建設分野で求められる専門技術を学ぶ厚生労働省認定職業訓練校です。「人を育てる場としての企業でありたい」という創業当時からの想いから長野校・松本校・金沢校の3校を運営し、社員の技能・技術の育成を図っています。
インテリアサービス科・防水施工科の2学科が設けられ、入社後、学科と実技を1年間学び、技能照査に合格すると技能士補の資格を取得できます。3月には次々と若い技術者達が巣立っていき、実際の現場で活躍しています。

実習の様子
-

床材の切断 -

学科授業風景 -

学科テキスト -

講師による指導 -

階段実技実習 -

講師による実演指導
卒業生の声
Interview01
T.Suzuki2017年卒業
学園の授業で一番印象に残っているのは「タイルの型の取り方」の講義です。切り込みや図面の見方など基礎的な部分を丁寧に教われたことが、現在のスピード感のある仕事につながっていると感じています。卒業後の現場では、講師の代わりに先輩や上司が指導してくださいます。よく見て学び、少しでも多くのことを吸収し、お客さまに喜んでいただけるよう努力を続けたいと思います。
これから入学される皆さん、講師である一級技能者から教わることは、現場で非常に役立つことばかりです。よく聞いて、よく学んでください。

Interview02
K.Takizawa2022年卒業
学園ではカッターの持ち方など基礎中の基礎から、クロスの貼り方など実践的な分野まで幅広く教わりました。クロス貼りの授業ではクロスの目地の角を出すのに苦戦しましたが、講師のアドバイスのおかげでできるようになりました。わからないことをすぐに聞ける、とても貴重な環境で成長することができました。
学園で内装の基礎を徹底的に学んだことで、実際の現場で何か起きても、応用を効かせながらスムーズに対処できていると実感しています。これからも一級技能士の取得を目指しながら、お客さまはもちろんのこと、自分でも満足できる仕事をしていきます。

Interview03
M.Kodama2021年卒業
今では普段行っている床施工業務ですが、当時はまったくわからなかった糊の塗り方や圧着の仕方など、基礎を一から学びました。床に関する授業以外にも、学園では建築の基礎・基本をたたき込まれます。おかげで卒業後に現場で不測の事態が起きた時にも、柔軟に動くことができるようになりました。
すべて少人数での授業なので、うまくいかない部分も講師が根気強く、できるまで付き合ってくださいます。「床材の裁断」の授業では、数ミリでも断裁位置がずれると仕上がりが悪くなってしまうのでとても苦戦しましたが、繰り返し挑戦することでできるようになりました。
卒業後は一級技能士の取得を目標に掲げ、日々励んでいます。取得後も、更なる技術の向上を目指して、一つひとつの仕事に対して丁寧な仕上げを心掛けていきたいと思います。

講師紹介Instructors
-
01

田尻 実
担当科目:学科
-
02
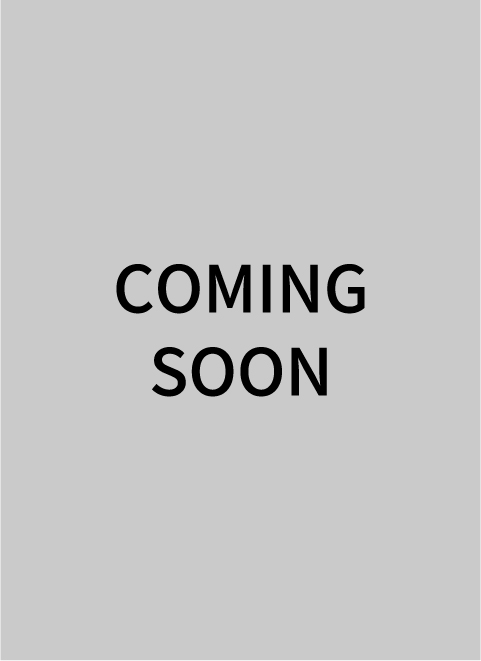
清水 清
担当科目:壁装
-
03

戸谷 宏一
担当科目:床